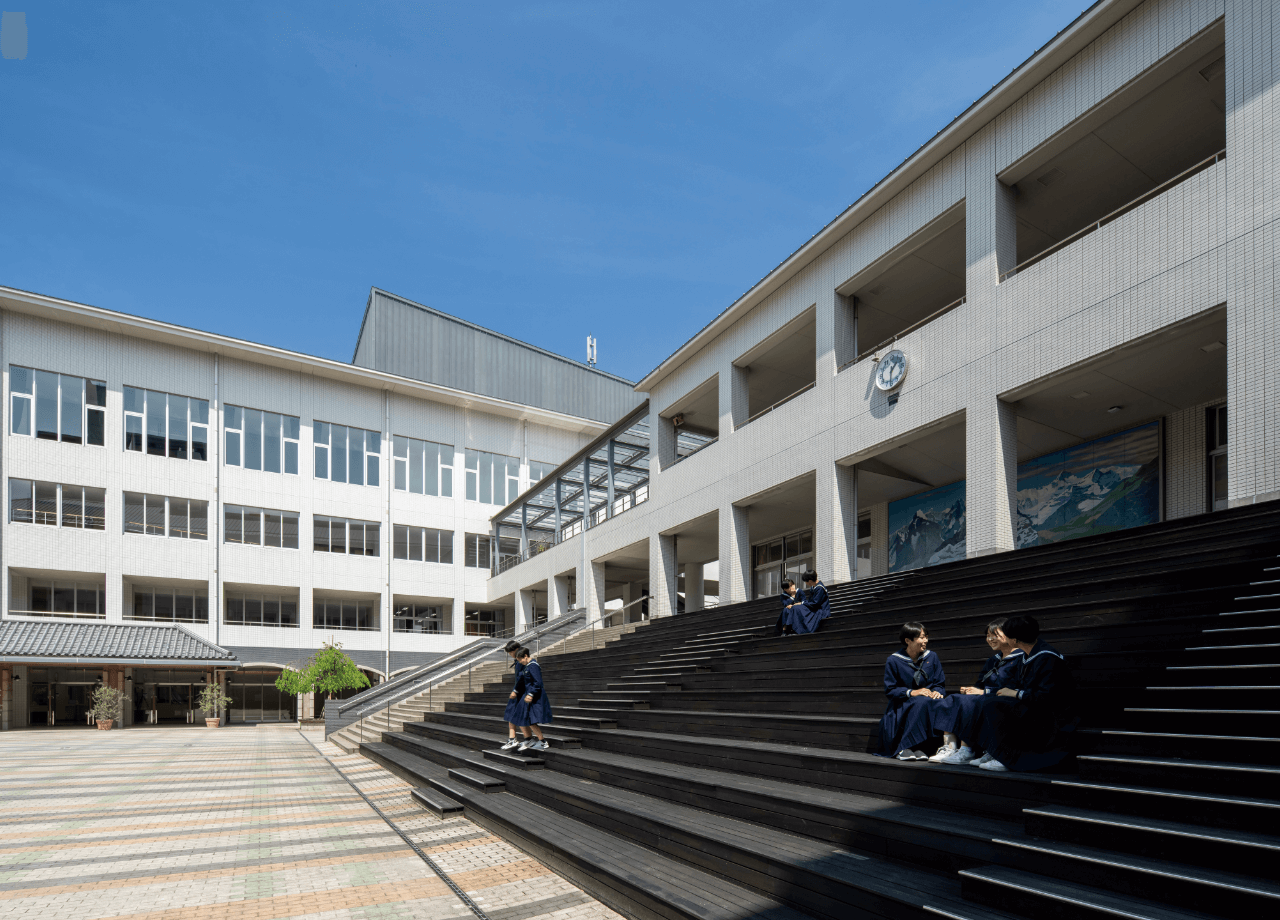たくさんの粒がないといけない。 たくさんの人がいて、ひとつのことができるんです。
やなせたかし
さて、問題です。アンパンマンのあん(餡)は、つぶあん(粒餡)でしょうか、こしあん(漉餡)でしょうか?
幼い子どもたちに人気のキャラクターと言えば、アンパンマン。生徒のみなさんも、随分とお世話になってきたのではないでしょか。「そうだ うれしいんだ 生きる よろこび たとえ 胸の傷がいたんでも♪」。「なんのために 生まれて なにをして 生きるのか♫」。ポップなメロデーの割には、実は哲学的な歌詞だなぁと感じた人もいるかもしれません。事実、アンパンマンには多様なメッセージが込められています。
では、では、冒頭の問いの答えは!? 正解は、つぶあんです。それではなぜ、つぶあんなのでしょうか。アンパンマンの作者であるやなせさんは、アンパンマンの餡が、つぶあんでなくてはならない理由を、次のように語っています。
「それには理由があるんです。たくさんの粒がないといけない。たくさんの人がいて、一つのことができるんです。こしあんにしちゃうと一粒ひとつぶが残らないでしょ。」
やなせさんは、戦争の時代を生きてきました。徴兵されて中国戦線に送られ、敗戦後に復員。しかし、最愛の弟は戦死……。戦争が何をもたらし、何を結果するのか。今月のことばには、戦争の暴力性、罪悪性を目の当たりにしたやなせさんの怒りが含意されています。それは、全体のために個人が犠牲を強いられていく社会への警鐘でもあります。
アンパンマンは、正義をふりかざし、敵を徹底的に打ち負かす超人的で強いヒーローではありません。困っている人に食べ物を分け与えながら、「力が出ない」と弱音もちゃんと吐くし、負けることだってある。ちゃんと弱さを持っています。弱いからこそ、いろんなキャラクターに支えられながら、「勇気100倍」となれる。誰かに助けられることで、誰かを助けていく―。
やなせさんと同じ時代を生きたスペインの哲学者・オルテガ(1883~1955年)は、ファシズム(全体主義)を支えた人びと(大衆)を、「みんなと同じ」であることに苦痛を感じないどころか、「みんなと同じ」であることを快楽として生きていく存在であると分析しました(『大衆の反逆』1930年刊)。一粒ひとつぶが、同じ一色に塗りつぶされ、同じであることに同調していく社会の先に、戦争があります。
みなさんの教室ではどうでしょうか? みんな同じ考えで、同じ性格、同じ趣味嗜好-。そんなわけありませんよね。一粒ひとつぶが違うから、時には対立もするし、わかりあえないこともある。だから、わかりあえないことにちゃんと向き合ってほしいと思います。「わかりやすさ」に抗い、「あいまいさ」に耐えていく。真っ白でも、真っ黒でもない、〝灰色の領域〟で粘り強く思考し、対話を重ねていく。こうした教室でのみなさんの小さな営みの積み重ねこそが、新たなファシズム、新たな戦争に対する大きな抵抗になると、私は希望を持っています。
今年は、「戦後80年」です。仏教界(浄土真宗)にも、戦争に積極的に加担したという重たい歴史があります。私自身も、自分事としてその歴史に向き合い続けたいと思います。
(文責:宗教科)