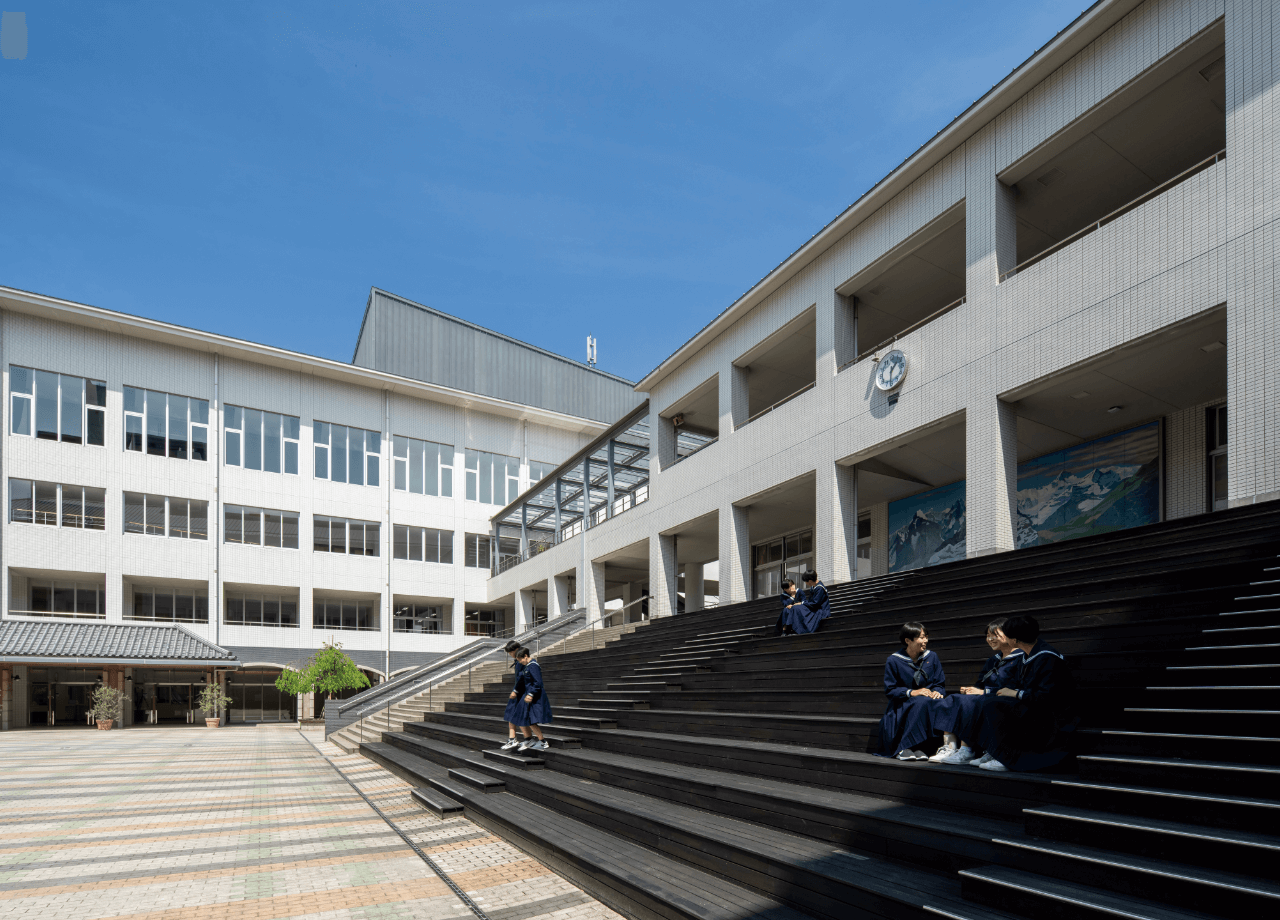朝は 希望に 起き 昼は 努力に 生き 夜は 感謝に 眠る
統計開始(1951年)以来、北部九州では最も早い梅雨明けとなりました。近年は、地球温暖化の影響か極端な雨の降り方に線状降水帯と呼ばれる現象が起きたり、夏になるとゲリラ豪雨という短時間に極端な降水量の雨が降る現象が起きたりするなど、ここ数年で私たちの身近な気候も大きく変わってきました。また、梅雨の季節といいながら真夏の暑さが全国に広がり、季節を感じるということもなくなりつつあるように思います。詩人で書家の相田みつを(1924-1991)さんの作品に「雨の日には雨の中を、風の日には風の中を」というものがあります。この詩は、雨の日には雨の日をそのまま受け止め共に生き、風の日には風の日をそのまま受け止め共に生きていくという、その時々の日々をそのまま受け入れて生きていくという意味の詩です。私たちは、雨が降る日を天気が悪いと口にすることがありますが、農作物や草木の生育にとっては雨の日は良い日となります。そのように考えてみると、立場によって見方が変わるように、私たちは天気だけでなく何事にも自分の都合や価値観で善し悪しを決めてしまっているように思います。相田さんの詩は、その日その時をそのままの縁として受け止めて生きていくことが大切であることをこの詩の中に込めて語られています。
今月のことばは、そのような日々をどのような気持ちで過ごしたらいいか、私たちにヒントを与えてくれる言葉ではないでしょうか。
浄土真宗の僧侶で教育者の東井義雄(1912-1991)先生の詩に、「目ざめてみたら生きていた」という作品があります。
目がさめてみたら 生きていた 死なずに生きていた
生きるための 一切の努力をなげすてて眠りこけていた わたしであったのに
目がさめてみたら 生きていた
劫初以来一度もなかった まっさらな朝のどまんなかに 生きていた
いや 生かされていた
私たちは、朝目が覚めることを“当たり前”と思っていますが、よくよく考えてみると目が覚めるということは、不思議なことであると語られています。さらに、最後の「生きていた いや 生かされていた」という一文は、目が覚めるかわからない私の目が不思議と覚めてまっさらな新しい朝を迎えた驚きと感動を表されています。私たちは、いつも“今日”“今”という時をいただいて生きています。しかし、その時を“当たり前”と受け取り、その大切さを忘れて過ごし、なかなかこの“今”を生きている有り難さに気づかずに生きているのが私たちの日々の有り様ではないでしょうか。だからこそ、ふとどこかで一度立ち止まって、自分の生き方や考え方を振り返る時間をもつことが大切です。それが、学校生活の中では礼拝の時間であったり、今月のことばを読む時間であったりしてほしいと願っています。そして、今年もこれから暑さが続く日々となっていきますが、今月のことばが表すような心がけをして、今日という毎日を、不思議な有り難い一日として精一杯歩んでいきたいものです。
(文責:宗教科)